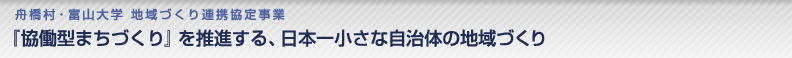平成24年度事業企画
第4次総合計画 協働のまちづくり推進
2nd Step ケーススタディ
舟橋村プロジェクトを解明しよう!動くプロジェクトとはいかに?
4日目 第4限舟橋村プロジェクトを解明しよう!動くプロジェクトとはいかに?
プロジェクトは何故動いた
開催日時:平成24年12月26日(木)18:00〜20:00
場所:舟橋村役場 2階会議室
舟橋村若手職員研修4日目では,舟橋村民憲章制定とふなはしまつりの改善事例から舟橋村と富山大学が連携して取り組んだプロジェクトの経緯や背景・プロジェクトが動いた仕組みと論理を学び,プロジェクトが動くため必要なActionや大学のナレッジを活用した住民・行政・大学の協働について考えるカリキュラムとした。
座談会.1
- 全員から一言プレゼン(前回の宿題)
- 進行:富山大学地域連携推進機構教授 金岡省吾氏
前回の研修宿題であった 「活性化する舟橋の姿とは」「あなた=行政職員はどうあるべき?」をテーマに各職員自身の考えを1人5分以内で発表。各人が考える地域が活性化している姿と舟橋村の現況と照らし合わせて意見を交換。村内での活性化している場所での状況や各人が接する課題などをふまえ,住民や行政職員の意識のあり方や行政がするべき役割を話し合った。

第4限講義
- プロジェクトは何故動いた
- 「舟橋プロジェクトを解明!」〜動くプロジェクトとは如何に?〜
村民憲章,ふなはしまつり改善プロジェクトをプロデュース - 講師 : 富山大学地域連携推進機構教授 金岡省吾氏
大学を取り巻く環境の変化から大学に求められる役割が,学術の中心,知的・道徳的・応用能力を展開しうる教育研究だけでなく,成果を広く社会へ提供し,社会の発展に寄与することが求められるようになり,特に地方国立大学では地域貢献機能を強化させ,地域社会の知識・文化の中核拠点,地域活性化の拠点として機能させることが命題となったと,富山大学では地域づくり・文化支援センター創設までの過程と背景を説明。富山大学と舟橋村の連携までの経緯を紹介し,舟橋村村民憲章策定プロジェクトとふなはしまつり改革プロジェクトの背景から活動概要と成果を解説した。

村民憲章策定では,綿密な打ち合わせをした策定方針の検討段階から住民参加のワークショッップを経て草稿案を完成,議会議決後に村民憲章が公表された過程を説明。大学が保持していた会議マネジメントノウハウや資料作成ノウハウ,協働型まちづくりには必須の手法であるワークショップ実施のノウハウが舟橋村へ移転されたことを話した。コンサルタント委託とは全く違う村と大学が役割を分担し,協働型まちづくりと憲章作成の関係や憲章,ワークショップ運営についてを両者が理解し,ワークショップから住民視点の言葉を引き出すとともに,舟橋を見つめ直し,絆づくりの礎となるなど取り組みの新鮮さは着実に目に見える成果を実感したことを解説。
継続的連携を望む声から包括連携協定を締結し,ふなはしまちづくり塾や行政職員の育成へ取り組んだ経緯を紹介し,ふなはしまつりの改革プロジェクトを解説。ヒアリング調査研究やワークショップにより住民による改革案を提案,住民主体のふなはしまちづくり協議会での企画運営により盛況なまつりが開催された事例から,協働型とは何か,実現への仕組みや住民主導での取り組み,人材の育成の重要性を示した講義となった。
座談会.2
- 質疑応答・討議
- テーマ:何故,ふなはしまつりは能動的に動くか?仕組みと論理は?
※当時の実情・課題→目標→方法論→成果検証
※今抱える業務で応用できることは如何に?
地域活性化が見える舟橋の姿とは? - 進行:富山大学地域連携推進機構教授 金岡省吾氏
本日の講義を受けての討議が行われ,村民憲章やふなはしまつりの事例を受けて何故舟橋村が動き出したかを参加者全員が意見や考えを述べ意見の交換がはかられた。ふなはしまつりが能動的に動いたのは自分たちが必要と感じた案件だったからという意見や各自に役割を与え,道を作ることで自発的意見が出しやすくなるなど環境づくり土台づくりの必要性や仕組みづくりの重要性について討議され,今後の課題解決への方向性を示すヒントをつかんだ。
総括・事務連絡
- 舟橋村 吉田昭博氏
研修の4日目を終えて,研修生へ向けて「地域の活性化について再度考えてみて欲しい。研修を受ける前の自分の言葉と研修後のの自分の言葉を比べてみてください」と総括をおこない,次回研修の予定と課題を案内し第4日目の研修が終了した。