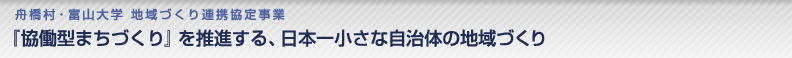平成24年度事業企画
第4次総合計画 協働のまちづくり推進
2nd Step ケーススタディ
舟橋村プロジェクトを解明しよう!動くプロジェクトとはいかに?
3日目 第3限舟橋村プロジェクトを解明しよう!動くプロジェクトとはいかに?
地域づくりの最前線1
開催日時:平成24年12月13日(木)18:00〜20:00
場所:舟橋村役場 2階会議室
舟橋村若手職員研修3日目では,地域が活性化する状態とは何かを学び,「地域が学び・考え・身の丈で行動する」地域主導で動いたまちづくりの事例から住民を動かし,協働でプロジェクトを動かす必要性を理解し,地域課題解決へ向けた協働のまちづくりについて考察。そのために行政は何をするべきかを各自が考えるカリキュラムとした。
座談会.1
- 全員から一言プレゼン(前回の宿題)
- 進行:富山大学地域連携推進機構教授 金岡省吾氏
前回の研修宿題であった 「これから求められる行政職員とは」「あなたは富山市で生き残れるか?生き残るためには何をすべきか?」をテーマに各職員自身の考えを1人5分以内で発表。各人の考える舟橋村における行政職員のあり方や理想,課題・意見を発表。舟橋村住民の顔が見える行政,住民に納得してもらえる行政,職員が広い視野を持ち,先を読み,地域を把握するスキルの重要性など各自の意見を出し合った。

第3限講義
- 地域づくりの最前線1
- 「地域主導で動くまちづくり」〜地域活性化とは何だろう?〜
最近気になるまちづくり 商店街・協働型まちづくり・・・ - 講師:富山大学地域連携推進機構教授 金岡省吾氏
地域が活性化している状態とはどんな状態だったのかを,実際に動き出したプロジェクトの事例を紹介し考察。全国で課題となる中心商店街活性化について考察し,抱える課題や中心商店街活性化政策の経緯を説明。地域主導で動き出した街づくりの事例として長野県塩尻市の協働で子育て支援と図書館を合築した市民交流センターでの,ボランティア・市民活動団体・企業が企画運営に参画し,協働を考える講演会や市民ワークショップを通じ施設のニーズ把握や利用者の新需要を生み地域課題を克服した事例を紹介。また,常陸太田市内の商店街でのお金をかけないで自ら考えて動く身の丈イベントでの成功事例,佐久市内の商店街での地域アンケートのデータを重視してニーズ把握のもと自ら発案し客数を回復させ,さらに人材育成によりマネージメント意識を高め,実務能力と実践能力を磨き,新事業を立ち上げて新規出店を促して,空き店舗対策とした事例を紹介。
元気な商店街では,行政主導から地域主導へ変化し,地域の人たちが基本設計から取り組み,行政はサポーターとしての位置にいること。自ら考え動く,身の丈のイベントで,データを重視し来客ニーズを重視して地域課題解決に自ら考えていると話した。また,県内での新たな地域づくりの取り組みの事例として魚津市の協働型まちづくりでの市民提案事業や地域特性事業等を紹介した。富山大学への相談事例として,富山市新富町のまちづくり,高岡の子育てセンター整備の事例も紹介。地域主導でまちづくりが動いた事例と背景から地域の活性化について何かを考え,地域課題解決へのヒントを探る講義となった。

座談会.2
- 質疑応答・討議
- テーマ:地域が活性化している状態とは何?
- 進行:富山大学地域連携推進機構教授 金岡省吾氏
本日の講義を受けての質疑応答と討議が行われ,地域が活性化している状態とは何か?事例紹介のあったプロジェクトが何故動き出したのか,協働は実現可能なの,実現するべきか否かを各自の意見を交換した。舟橋村での協働のまちづくりが展開されているイメージや現状の業務認識や行政職員のあるべき姿など参加者全員が意見を述べ,互いの考えや思いを話し合った。
総括・事務連絡
- 舟橋村 吉田昭博氏
研修の3日目を終えて,研修生へ向けて「今までの研修を振り返って仲間同士で話し合って,キーワード等を自ら考えてみて欲しい。今やっている事をベースに置かないで,自身で今のやり方を考えてみて欲しいと」と総括をおこない,次回研修の予定と課題を案内し第3日目の研修は終了した。