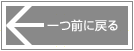明珍火箸他 ミョウチンヒバシ


資料番号
K-049
種別
金属
材質
鉄
技法
鍛造
規格
茶席用火箸,床置物海老
産地
兵庫
制作者
明珍本舗
制作年次
明珍火箸は、原料の鉄を高温に熱し、赤く輝いている状態で金槌によって打ち延べ、一つ一つ作られる。
いわゆる鍛冶と呼ばれる仕事だ。
鉄という素材と鍛冶という仕事が生み出したこの火箸は、紐で吊るし互いをれ合わせると、鈴虫の声色のような澄んだ、深い余韻を持つ音を響かせるのが特徴である。
この音は長年SONYのマイクロフォン開発のテスト音源として使用され、SONYマイクの品質を一躍世界の水準となるまでに高めた。
現代のエンターテイメントにおける音響システムの発展は、この火箸なくして起こり得なかったのである。
現在、明珍火箸を鍛えている明珍宗理さんは、明珍家52代目にあたる。
明珍家は平安時代から続く甲冑を作る鍛治師である。
平安時代、近衛天皇に武具を献上した際に「音響朗々、光明白にして玉の如く、類稀なる珍器なり」と、『明珍』の二字を賜ったという。
その後、千利休に請われて茶席用の火箸を作ったのが明珍火箸の始まりと言われている。
明珍家は明治維新となるまで甲冑の名品を数多く生み出してきた。
そしてその技術は、自在物といわれる海老や鳥、龍、蛇、虫などを模した関節を自在に動かすことのできる置物に顕れている。
代々の、実物と見まがうほどの名品を博物館等で見ることが出来る。