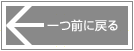銀器の歴史は古く延喜式(916年)に見られる。
また法隆寺の献納御物の中にも各種の銀器製品がみられ,さらには江戸期の初期(1624〜1644)に銀道具類が調整され,皇室あるいは将軍に献上された記録がある。
これらの銀器を制作した職人を銀師(しろがねし)と称した。
彫金技法が元禄期(1670〜1733)に大名,武家の使用する家彫から町人の持物である町彫へと技法の進展にともない,その製品の生地(下地づくり)を作ったのが白銀師であった。
つまり下請的な存在である。
明治以降,鍛金師として現在の東京銀器の基礎となっている。
昭和54年,国の伝統産業工芸品の指定を受けている。
鍛金技法の材料は銅,真鍮,鉄が主であるが銀を主体とした産地は他には殆んどない。
従って,銀器の特長は他産地の金工製品と大きく異なっているといえる。