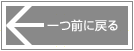コンド族真鍮像 コンドゾクシンチュウゾウ

コンド族真鍮工芸についての報告書が初めて出されたのは,今からおよそ160年前である。
中央インドの南東部に位置するコンド地方の真鍮工芸は,(1)地田神崇拝を認める大多数によって,人身御供の際使用された孔雀と雄牛,(2)血縁集団の象徴である氏族トーテムとしての動物,魚,鳥,爬虫類,(3)花嫁の嫁資としての小さな立像群,兵士を乗せた象や馬,(4)装飾や種々雑多な用途のための物,これら4つの目的で作られた。コンド族は,彼ら自身では真鍮工芸を創らず,村から村を移動しながら鋳造を生業としたドクラによって生産された。
コンド族の人身御供が近年放棄され,独特の慣習や宗教と供に,真鍮工芸も姿を消していった。
日本を含むアジアの伝統的蝋型鋳造技法の中でも,蜜蝋を糸状(蝋糸)にし,それを中子に巻きつけて蝋原型を成形する方法は,ドクラ独特の技法である。
現在もインドの数州において,蝋糸を使った鋳造がドクラによって行われているが,かつてのコンド族の宗教的にも社会的にも重要な意義を持つ真鍮工芸は,今はもうつくられていない。